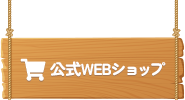庭に落ち葉が溜まり、処理に困ったことはありませんか?実はそのまま捨てるのはもったいない!
落ち葉は、ちょっとした工夫でふかふかの堆肥に生まれ変わります。しかし「簡単な作り方がわからない」「うまく堆肥にならずに失敗しそう」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、初心者でも簡単にできる落ち葉堆肥の作り方を5つのステップでご紹介します。さらに、「失敗しないためのコツ」についても詳しく解説。あなたも自宅で土壌改善に役立つ堆肥を作れるようになります!
身近な落ち葉を資源に変えるため、堆肥作りにチャレンジしてみませんか?ぜひ最後までチェックしてみてください!
落ち葉堆肥の基本
落ち葉堆肥は、家庭菜園やガーデニングに最適です。土壌の通気性や保水性を向上させ、植物が元気に育つ手助けをしてくれます。さらに、無料で作れるので、堆肥代を節約できるのもうれしいポイントです。
落ち葉堆肥の基本を以下の観点から解説します。
- 落ち葉堆肥は人の手で作る腐葉土
- 落ち葉堆肥のメリットは通気性や排水性の向上
- 落ち葉堆肥には落葉広葉樹がおすすめ
まずは落ち葉堆肥の基本的なポイントを押さえていきましょう。
落ち葉堆肥は人の手で作る腐葉土
落ち葉堆肥とは、落ち葉を微生物の力で分解させ、土のような状態にしたものです。見た目や働きは腐葉土と似ていますが、人の手を加える点が異なります。
森林では、落ち葉が自然に積もると数年以上をかけて腐葉土に変わります。自然に任せるままだと、堆肥として使用するには時間がかかりすぎます。そのため人が空気や水、窒素や炭素などの栄養分を与えて分解を早めたものが落ち葉堆肥です。
落ち葉堆肥を自分で作れば、家庭菜園の土壌を改良するのに使えます。栽培する作物も元気に育ちやすくなるでしょう。自然由来の堆肥として役立ちます。
特に庭に落ち葉がたくさん出る家庭では、ゴミにせず堆肥にするのがおすすめです。
落ち葉堆肥のメリットは通気性や排水性の向上
落ち葉堆肥の最大の利点は、土の通気性と排水性の改善です。植物の根が呼吸しやすくなり、水がたまりにくくなるため、根腐れのリスクが減ります。
落ち葉堆肥には水分を保つ力もあります。水はけが良くなる一方で、適度な水分をキープ可能です。そのため植物に適切な量の水が届きやすくなります。乾燥しやすい季節や地域でも、土が乾きすぎるのを防げるでしょう。
落ち葉堆肥には落葉広葉樹がおすすめ
落ち葉堆肥を作るなら、落葉広葉樹の葉がおすすめです。薄くて分解しやすいため、堆肥作りがスムーズに進みます。
具体的にはカエデ・ケヤキ・クヌギなどが良いでしょう。逆に、スギやヒノキなどの針葉樹は分解に時間がかかる傾向があります。落ち葉堆肥作りに慣れていないなら、落葉広葉樹の葉を中心に集めると失敗しにくくなります。
落ち葉に加えて枯れ草や小枝を混ぜても問題ありません。ただし、大きな枝は分解が遅いため、細かく砕いてから混ぜるのが良いでしょう。
近くに公園や落ち葉が多い場所があるなら、そこから集めるのもひとつの方法です。ただし、公園によっては落ち葉の持ち出しが禁止されています。トラブルを防ぐために、事前にルールを確認してから集めてみてください。
初心者でもできる!落ち葉堆肥の作り方5ステップ
落ち葉堆肥を実際に作る具体的な手順を5ステップに分けて説明します。
- 必要なものを準備する
- スペースを確保する
- 落ち葉と土を交互に積み重ねる
- 水が全体に行き渡るようにかける
- 踏み固めて圧縮する
初心者でも取り組みやすい方法なので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。
必要なものを準備する
まずは、作業に必要な道具や材料を準備しましょう。特別な機械は不要ですが、効率よく作るためには準備が必要です。
基本の道具は以下のとおりです。
- 落ち葉
- 園芸用スコップやシャベル
- 軍手
- 適量の土
- 米ぬか
- ホースやじょうろ
大量の落ち葉を使うなら、運搬用に大きめの袋や容器も用意すると便利です。
スーパーやホームセンターで手に入るダンボールを使って作る方法も人気があります。大きめのダンボールの底を抜いて落ち葉堆肥を仕込むと、保管もしやすくなります。
スペースを確保する
落ち葉堆肥を作る場所は、風通しが良く、水はけの良い環境が理想です。日当たりの強い場所や雨がたまりやすい場所は避けたほうが安心です。
可能であれば、日陰になる場所を選んでください。直射日光が長時間当たると、必要な水分が失われやすくなります。ただし、風通しが悪いとカビや臭いの原因になるので注意してください。
一度にたくさん仕込めば効率的です。できるだけ大きめの容器や積み上げスペースの準備をおすすめします。
落ち葉と土を交互に積み重ねる
堆肥作りで大切なのは、落ち葉に土や微生物のもとになる材料を加えることです。落ち葉がより分解されやすくなります。
確保したスペースに落ち葉を一層敷きます。その上に土を薄く重ねてください。この作業を何度か繰り返し、層を積み重ねるのがコツです。米ぬかを混ぜると、より発酵が安定して栄養価の高い堆肥になります。
落ち葉と土を積むときは、大きな枝や石を取り除きましょう。異物が混じると分解が遅れ、完成までに時間がかかるからです。
しっかり層を作ると、発酵が進みやすくなります。失敗を避けるためにも、丁寧に積み重ねていきましょう。
水が全体に行き渡るようにかける
水分は微生物が働くために必要です。落ち葉が乾きすぎると分解が進まず、堆肥になりません。
落ち葉と土を重ねるときに、全体がしっとりする程度に水をかけましょう。水をかけすぎると空気が通りにくくなり、腐敗の原因になるので注意してください。土や落ち葉が濡れすぎているときは、水分を飛ばす工夫が必要です。
湿度がちょうどよいと、微生物が活発に働き始めます。発酵が進むと熱が出て、手を入れるとほんのり温かく感じられるでしょう。これは堆肥が順調に発酵、分解されているサインです。
踏み固めて圧縮する
最後に、積んだ落ち葉と土を軽く踏み固めてください。「踏み固めると空気が入らないのでは?」と不安になるかもしれません。
ですが少し圧力をかけると落ち葉と土が密着し、微生物が分解しやすい状態が整います。まったく固めず隙間だらけだと、発酵しづらくなるので注意が必要です。
落ち葉を踏み固めた後は月に1回以上の切り返しをしながら、数カ月から半年ほど自然に発酵が進むのを待ちましょう。
完成の目安は、見た目と匂いが腐葉土に近づいたときです。気温や季節、落ち葉の種類によって時期は前後しますが、じっくり発酵を待ってみてください。
落ち葉堆肥作りを失敗しないためのコツ
落ち葉堆肥作りは簡単ですが、いくつかのポイントを押さえておけば失敗がぐっと減ります。ここでは、特に重要な4つのコツを解説します。
- できるだけ大量に作る
- 雨による水たまりに注意する
- 月に1回以上切り返しをする
- 完熟を確認してから使用する
それぞれ見ていきましょう。
できるだけ大量に作る
落ち葉堆肥はある程度のボリュームがあったほうが、堆肥化のスピードや品質が安定しやすくなります。
微生物の働きによって発生する熱が逃げにくくなるためです。少量の落ち葉だと発酵熱が足りず、堆肥化が進みにくい傾向があります。40〜90cm程度を積み上げるのがおすすめです。
一度にたくさん仕込めない場合でも、少しずつ積み重ねていく方法で問題ありません。ある程度の厚みと量を確保し、微生物が働きやすい環境を整えましょう。
雨による水たまりに注意する
堆肥は適度な湿度が必要ですが、水が多すぎると腐ってしまいます。特に梅雨や台風の時期は、大雨が一度に降るため注意が必要です。
落ち葉の中に水がたまっていた場合は、かき混ぜて水分を均一にしてください。新聞紙やダンボールを混ぜて、水分を吸収させるのもおすすめです。
通気が悪くなると、空気を嫌う菌が増えて腐敗しがちです。一度腐敗すると、完成まで時間がかかるだけでなく、においで周囲に迷惑をかけるおそれもあります。
水に浸った状態では酸素が足りず、微生物がうまく働けません。雨ざらしの状態で堆肥を作る際は、雨で水分が多くなりすぎないよう対策しましょう。
月に1回以上切り返しをする
堆肥作りを順調に進めるには、定期的な切り返しが重要です。切り返しとは、積んだ落ち葉や土をスコップなどで混ぜる作業です。
切り返しによって空気が全体に行き渡り、微生物が活発に働きます。温度と湿度が均一になりやすく、堆肥の質も良くなるでしょう。
目安としては月に1回以上ですが、気温や湿度によっては2週間に1回程度でもかまいません。特に夏など気温が高い時期は発酵が早く進み、臭いが出やすくなります。温度が50度以上になったら、混ぜて空気を入れると良いでしょう。
切り返しのときは、全体を均等に攪拌(かくはん)するよう意識してください。全体の発酵が均一に進みます。手間はかかりますが、早く質の良い堆肥が作れます。
完熟を確認してから使用する
落ち葉堆肥を発酵しきっていない状態で使うと、作物に負担がかかります。根を傷めて枯れる恐れがあるため注意が必要です。
完熟とは、色や匂いが腐葉土のようになり、落ち葉の形がほとんど分からなくなった状態を指します。手で触ったときにサラサラとした土のような感触があれば、完成と考えてよいでしょう。
完熟までの期間は3ヵ月〜1年が目安です。ただし、季節・落ち葉の種類・切り返しの回数によって時間は大きく変わります。焦らずに、微生物の働きをゆっくり待つのが成功のコツです。
無料の落ち葉で堆肥を作ろう!
落ち葉堆肥作りは、費用をあまりかけずに始められます。無料で手に入る落ち葉を再利用できる点は、大きな魅力です。
最初はうまくいかなくても、落ち葉の種類や量、切り返しのタイミングを調整するうちにコツがつかめてきます。身近な落ち葉をうまく活用して、自分だけの「エコな循環」を楽しんでみてください。
「堆肥作りはちょっと大変…」と感じている方には、100%オーガニック堆肥「BOROの輝き」がおすすめです。
天城の自然と健康な馬が育んだこの堆肥は、すぐ使える完熟タイプです。自分で積み重ねや切り返し、水分管理といった堆肥作りの手間をかけることなく、ふかふかで上質の土に整えられます。そのため時間や手間をかけずに土づくりを始めたい方にぴったりです。
手軽なのに、しっかり育つ。その違いを、ぜひ体感してみてください。